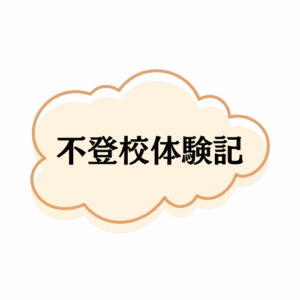🌷クラスで浮いていた子が伝えたい、不登校の本当の姿

こんにちは、しば子です🐾
今日は少し勇気を出して、
昔の私のことを書いてみようと思います。
「不登校」って聞くと、
なんだか重たく感じるかもしれません。
でも、あの頃の私はただ“必死に生きていた”だけなんです。
1️⃣ 小さなころの私
小学1年生のとき、もう授業についていけませんでした。
文字を覚えるのも遅く、計算も苦手。
忘れものも多くて、先生に「またか!」と怒られては、
胸の奥がきゅっと痛くなっていました。
それでも低学年の頃は、
「うるさい子」「元気な子」として笑ってごまかせていた気がします。
でも学年が上がるにつれ、周りとの“差”が広がっていきました。
気づけば私は、“陰キャ”と呼ばれる側になっていきました。
2️⃣ 先生からからかわれた日々
黒板の字が見えなくなっても、
「見えない」と言う勇気がありませんでした。
「またサボってる」と誤解されるのが怖かったから。
そんな私に先生は笑いながら言いました。
「ちゃんと見なさい、見えてるでしょ?」
その場の空気が凍りついて、
私は笑うこともできずに下を向きました。
3️⃣ 「変な子」と呼ばれても必死だった
ピアノの発表会で立候補したときも、
「ほんとに習ってるの?」と疑われて。
でも私は、注目されたいとか、目立ちたいとかよりも、
“ここに居たい”ただそれだけでした。
4️⃣ 中学での孤立
「は、どうぞ」と笑って支柱を渡しただけなのに、
男子に舌打ちされて、
「あ、もう小学校の頃みたいに素直ではいられないんだ」って気づきました。
そのうち、「死ね」と言われるようになり、
体育では「この子とペアはいや」と避けられ、
50メートル走のペアも誰もいない。
教室中の視線が刺さって、消えたくなりました。
5️⃣ 立候補して、また失敗して
「普通の子になりたい」
その思いで学級委員や応援団に立候補したけれど、
発達の特性や不器用さからミスをして、
先輩に怒鳴られてしまうこともありました。
努力すればするほど浮いてしまって、
「やっぱり私は変なんだ」と思い知らされていました。
6️⃣ 教室に入れなくなるまで
次第に、教室に行くのが怖くなりました。
保健室に逃げる日が増えて、
先生に「泣いてもいいから教室に行きなさい」と言われたとき、
涙より先に「分かってもらえない」って気持ちで胸がいっぱいになりました。
7️⃣ 高校でも変わらなかった現実
「高校デビューだ!」と意気込んでも、
話せば笑われ、黙れば「無口で変な子」。
結局、また孤立してしまいました。
それでも、諦めきれずに何度も通おうとして。
だけど、母を亡くしたことで心の支えがなくなり、
不登校に拍車がかかりました。
8️⃣ 「変な子」に見える子へ
もしクラスに、ちょっと浮いてる子がいたら、
どうか「わざと」だなんて思わないでほしい。
その子はその子なりに、
必死に生きてるんです。
優しくしたい、笑っていたい、
そんな気持ちはみんな同じです。
9️⃣ 不登校は「逃げ」じゃない
不登校は「怠け」でも「逃げ」でもありません。
その子がその子のペースで、
生きている証なんです。
私はずっと「浮いていた子」だったけど、
いまは農業やハンドメイド、ブログを通して
“私らしい道”を歩けています🌿
🔟 これから伝えていきたいこと
もしクラスに「変わってる」と言われる子がいたら、
少し立ち止まって、見てほしい。
その子は“違う形”で生きているだけ。
違っていてもいい。
それでも未来はつながっている。
私も、そんなメッセージを
これからも伝えていきたいと思っています🌷
💌 最後に
同じように苦しんでいる子へ。
そして、その子を見守る大人の方へ。
私はカウンセリングのスキルをもっていませんが、それでもよければお問い合わせ頂けたら私の経験談や私なりの対策をお伝えします🐶
それで解決するわけではありませんが気休めになれたら嬉しいです。
もちろんお金は頂きません!
お友達として繋がれたら嬉しいです^^
しば子より🐾💕
▶ お問い合わせは お問い合わせからお願いいたします。